食べる順番が注目されています。
その中でも、タンパク質をどのタイミングで摂取するのが良いのか、疑問に思っている人が多いようです。
そこで、下記の疑問に答えます。
- 食べる順番なんて意味ないのか?
- なぜ私は食べる順番で痩せることができたのか?
- 食べる順番はタンパク質からいくべきか?
というわけで、本記事のテーマは、下記のとおりです。
食べる順番はタンパク質から摂取すれば痩せるのか?
本記事では「食べる順番を見直すことから痩せていきたいけど、どうすればダイエットに効果がるのか分からないよ…教えて!」という方に向けて書いています。
この記事を読むことで、「食べる順番の効果とその実践方法」までをイメージできるようになると思います。
「痩せたいな~」と感じていた私を救ってくれたのが食べる順番でした。
ダイエットが苦手な私でも続けられている、「食べる順番」というダイエット方法に感謝の気持ちを込めつつ、記事を執筆します。
それでは、さっそく見ていきましょう。
食べる順番なんて意味ないのか?
意味大ありです。
食べる順番の意味を理解するためには、下記の点を押さえておきましょう。
- 太るメカニズム
- 痩せるメカニズム
- 食べる順番遵守こそ糖質制限の入門編
太るメカニズム
まずは太るメカニズムです。
食後の血糖値上昇が太る原因です。
食事をするとインシュリンが分泌され、活動するためのエネルギーである「糖」を体中に届けます。
体中に糖が行き渡ってもまだ糖が残っている場合、インシュリンが残った糖を今度は「脂肪」にして体中に届けます。
この段階で私たちは「なんか最近太ったな~」と実感するのです。
いわば、脂肪は糖の備蓄しておく倉庫と考えると分かりやすいですね。
痩せるメカニズム
というわけで、この「糖」を制限することこそ痩せる近道であり、ダイエットの常道ということになります。
こうした糖質制限は、体中に糖が行き渡ってもまだ糖が残っている状態にならないよう糖を減らして、活動するエネルギーだけに留められるよう食生活をコントロールすることを言います。
原理主義的な糖質制限は、活動エネルギーまでも不足させる戦略を取ります。
そうなると当然、体は正常に活動できません。
そこで、例の備蓄してある脂肪から糖を運び出して活動エネルギーとして使用します。
その結果、備蓄してある脂肪が徐々に減り、痩せていくのです。
以上が原理主義的な糖質制限ダイエットになります。
食べる順番遵守こそ糖質制限の入門編
しかし、この原理主義的な糖質制限は、かなりの空腹を伴うダイエット方法であることは容易に想像がつくでしょう。
つまり、持続可能なダイエット方法ではないのです。
持続可能でなければ当然、その効果も期待できません。
そこで、食べる順番の登場です。
食べる絶対量を最初から減らそうとせず、自然に血糖値上昇を抑え、糖の摂取も最終的には減らしていくことを目指すのです。
繰り返しになりますが、太る原因は、食後の血糖値上昇にあります。
この血糖値の上昇自体は仕方のないことです。人間の体のメカニズム上、当然のことなのですから。
そこで、その血糖値の上昇をゆっくり上昇させることにします。
そうすることで、太りにくくなります。
糖質、つまり、ご飯やパン、麺類といった食材は、血糖値を上昇させる親玉です。
偉そうに教科書的に言えば、5大栄養素とは下記のとおりです。
糖質も私たちの生命維持に欠かすことのできない5大栄養素のひとつですが、ほかの栄養素と比較して、安くておいしいものばかりです。
よって、どうしても摂取過多に陥ってしまいがちです。
しかも残念なことに、血糖値の上昇ランキングは下記のとおりです。
- 糖質
- 脂質
- タンパク質
- ビタミン類、ミネラル類
簡単に言えば、ご飯やパンなどの糖質はすぐに血糖値が上がる。太りやすい。
一方で、野菜や肉魚豆類などのタンパク質は血糖値が上がりにくい。太りにくい。一般的には痩せる食材と形容されたりもしますね。
というわけで、発想の転換をしてみます。
この血糖値が早く高くなる順番と逆の食生活を実践できれば、血糖値が上がりにくくなります。
つまり、食べる順番を下記のとおり実践できればダイエットに効果があるのです。
まさに、上記こそ「食べる順番」です。
さて、ここで今回のテーマである「食べる順番はタンパク質から摂取すれば痩せるのか?」にようやく話を戻します。
上記のとおり「ご飯、パン、麺類、野菜の根菜類、果物などの糖質」と比較して「卵、魚、肉、豆類、ヨーグルト、納豆などのタンパク質」は、血糖値の上昇はかなり緩やかです。
よって、「タンパク質から摂取すれば痩せるのか?」といわれれば、痩せる!といえます。
ちなみに、血糖値の上昇が緩やかなのは、ゆっくり栄養を吸収しているからです。
よって、体への負担も少ない点もメリットとといえます。
あとはよく噛んで食べるなどの巷でよく聞く方法なども随所に取り入れていけば、さらに糖質の摂取量を減らすことができて、グングン痩せていくことできます。
なぜ私は食べる順番で痩せることができたのか?
結論としては、食べる順番を正しく実践して、血糖値の上昇を抑えることができたこと、そしてご飯や甘いものなどの摂取量を減らすことができたからです。
食べる順番を「正しく」実践する上でのポイントは下記のとおりです。
- 各食材の特徴を知る
- 各食材の自分自身との相性を試す
- 効果を検証する
各食材の特徴を知る
人間食べなければなりません。そして、食べることは楽しみでもあります。
だから、食べる順番を気にしつつも、自然体で食生活を満喫できてこそ、持続可能な食べる順番の実践につながります。
それには、太る食材を知っておく必要があります。そして、その太る食材の摂取を減らして、かつ、その太る食材の食べる順番をラストに持っていく!ことが重要です。
下記の順に太ります。
1野菜や海藻類、2卵、魚、肉、豆類、ヨーグルト、納豆などのタンパク質は、太るというよりはむしろ痩せる食材に分類されます。
太るのは、3ご飯、パン、麺類、野菜の根菜類、果物などの糖質です。
各食材の自分自身との相性を試す
しかし、人間は機械ではありませんから、燃料のようにただ体内に入れればよいというわけにはいきません。
野菜、タンパク質、ご飯という食べる順番にひたすら固執するのは、おすすめできません。
例えば、おいしそうなチャーハンが出てきたとして、いきなりそのチャーハンから食べるのはさすがに良くありません。
しかし、サラダとバンバンジーも同時にあるのだとしたら、まずはサラダとバンバンジーを半分食べてからチャーハンを一口、そして、サラダを一口、そしてバンバンジー…みたいな感じで、食べたいと思うでしょうし、実際、それで良いのです。
なにがなんでも、野菜を全部食べて、次にバンバンジー、次に、チャーハンという順に自分の食生活を縛る必要はないのです。
ぜひ、自分の満足感のいく食べる順番の確立を目指してください。
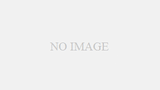
食べる順番とは、ご飯をできる限りラストに持っていくことで血糖値の上昇を抑え、ご飯や甘いものなどの糖質自体の摂取量を減らすことを目的としているわけですので、正しい食べ方は一つではないのです。
効果を検証する
体重は年に一度の人間ドックの時にはかるだけという人がいます。
しかし、それではだめです。
せっかく食べる順番を実践しているのですから毎朝はかりましょう。
そして、食べる順番の効果を毎日確認するのです。
ポイントは、体組成計を導入することです。
体組成計なら体重、BMI、内臓脂肪レベル、体内年齢まで出してくれます。
もちろん、あくまでも参考値に過ぎません。
しかし、ご飯を多く食べた翌日は私の場合確かに、体重や内臓脂肪レベルが上昇しているので食べる順番の重要性を再認識させてくれます。
体組成計の値段もぴんきりですが、3,000円程度のものを私は愛用しています。つくづく今は良いものが安く手に入る時代になったものだと感じます。
食べる順番はタンパク質からいくべきか?
タンパク質「から」にこだわる必要はありません。
食べる順番とは、繰り返しになりますが、古典芸能のようにこういう型で食べねばならない!という前例があるわけではありません。
あくまでも、ご飯をできる限りラストに持っていくことで血糖値の上昇を抑え、ご飯や甘いものなどの糖質自体の摂取量を減らすことを目的としているだけですので、自由な発想で、気軽に食生活を楽しんでください。
その際には、毎朝の体組成計での効果の検証は毎日行ってください。
始めは中々、効果は実感できないかもしれませんが、最低でも1年は食べる順番を意識して、体組成計での観測を続け、トライ&エラーを継続していけば、必ず効果が表れてきますので、一緒に頑張っていきましょう。

コメント